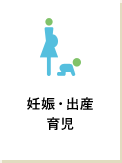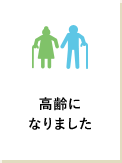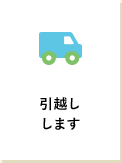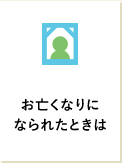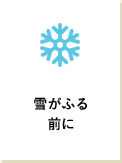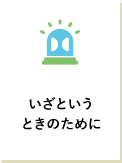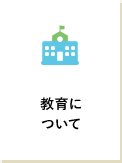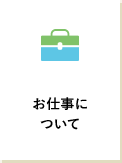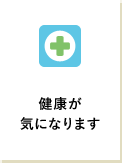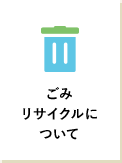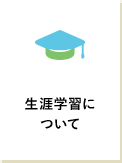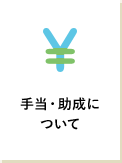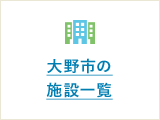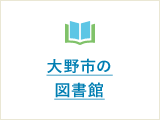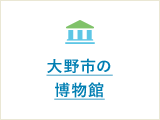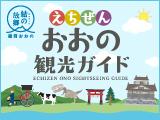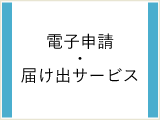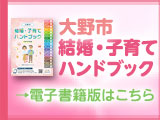大野市では、次の行事等を「おおの遺産」として認証し、次世代への継承を支援しています。
| 認証番号 | 1 |
|---|
| 認証日 | 平成29年3月27日 |
|---|
| 分野 | 生活 |
|---|
| 名称 | 七間朝市 |
|---|
| 団体等名 | 大野市朝市出荷組合 |
|---|
| 特色 | 金森長近が城下町を整備した際に開いた市が始まりといわれています。
近隣の農家が野菜などを持ち寄り、町の人々の食料調達の場として続いてきました。現在は 出荷組合が結成され、朝市の継続に努めています。 |
|---|
| 認証番号 | 2 |
|---|
| 認証日 | 平成29年3月27日 |
|---|
| 分野 | 伝統芸能 |
|---|
| 名称 | 蕨生 里神楽 |
|---|
| 団体等名 | 里神楽実行委員会 |
|---|
| 特色 | 明治15年に、篠座神社の里神楽に習い、以後春祭りに奉納しています。
翁と婆が道化役をします。 |
|---|
| 認証番号 | 3 |
|---|
| 認証日 | 平成29年3月27日 |
|---|
| 分野 | 伝統芸能 |
|---|
| 名称 | 篠座神社の里神楽・豊栄舞 |
|---|
| 団体等名 | 篠座神社獅子舞保存会 |
|---|
| 特色 | 神楽の起源は最も古く、平安時代と考えられます。一時途絶えていましたが、平成7年から、再び毎年実施するようになりました。
豊栄舞は平成24年から、小学生が 巫女の舞をしています。 |
|---|
| 認証番号 | 4 |
|---|
| 認証日 | 平成29年3月27日 |
|---|
| 分野 | 伝統芸能 |
|---|
| 名称 | 木本領家里神楽 |
|---|
| 団体等名 | 木本領家区 |
|---|
| 特色 | 明治38年に篠座神社の神楽を伝承し、豊作を感謝し秋祭りに奉納しています。
小中学生のみこしや踊りを行い、地域の若い世代が関わりを持てるよう工夫しています。 |
|---|
| 認証番号 | 5 |
|---|
| 認証日 | 平成29年3月27日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 木本区初午だんご撒き |
|---|
| 団体等名 | 木本区 |
|---|
| 特色 | 大火事の故事から、火除けの行事として伝わっています。木本は5つの行政区からなり、それぞれが団子を作って持ち寄り、参拝客に団子をまきます。 |
|---|
| 認証番号 | 6 |
|---|
| 認証日 | 平成29年3月27日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 篠座神社の福もちまき |
|---|
| 団体等名 | 篠座神社総代会 |
|---|
| 特色 | 昭和50年からはじめたもので、市内外から多くの人が福を求めて参拝します。 |
|---|
caption| 認証番号 | 7 |
|---|
| 認証日 | 平成29年3月27日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 篠座町の旧家が持ち回る神明講 |
|---|
| 団体等名 | 篠座神社と篠座町(旧家23軒) |
|---|
| 特色 | 篠座神社を含めもともとの集落(篠座村)を構成している旧家で継承されている伊勢講の影響を受けた行事です。年3回行われます。 |
|---|
| 認証番号 | 8 |
|---|
| 認証日 | 平成29年3月27日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 上大納左義長 |
|---|
| 団体等名 | 上大納区 |
|---|
| 特色 | 旧暦小正月にナラ、杉、わらで左義長構造物を作り、各戸で用意した裁縫の上達を願う「つつみ」と字の上達を願う「書初め」をつけます。現在は2月14日に行われています。 |
|---|
| 認証番号 | 9 |
|---|
| 認証日 | 平成29年3月27日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 尾永見伊勢講 |
|---|
| 団体等名 | 尾永見神社 |
|---|
| 特色 | 伊勢代参は行いません。伊勢神宮奉納のためのお神田がありましたが、その跡を石碑を立て保存しています。料理の献立のきまりを、続けています。 |
|---|
| 認証番号 | 10 |
|---|
| 認証日 | 平成29年3月27日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 鍬掛伊勢講 |
|---|
| 団体等名 | 鍬掛伊勢講保存会 |
|---|
| 特色 | 代参人を決め、代参後には「はばきぬぎ」をして、お札やお神酒を分け合うという伊勢講の形をよく残しています。 |
|---|
| 認証番号 | 11 |
|---|
| 認証日 | 平成29年3月27日 |
|---|
| 分野 | 景観 |
|---|
| 名称 | 行人岩 |
|---|
| 団体等名 | 大矢戸区 |
|---|
| 特色 | 道元禅師由来の修験遺跡として多くの修験者がこの岩屋で修業をしたと伝わっています。
参拝者が増え、大矢戸区が登山道を含めて保存活動を続けています。 |
|---|
| 認証番号 | 12 |
|---|
| 認証日 | 平成30年3月22日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 伊勢講 |
|---|
| 団体等名 | 土布子区 |
|---|
| 特色 | 江戸時代、洪水が起きた時に集落の伊勢堂という祠に流木が引っ掛かり濁流が左右に分かれ難を逃れたことから、伊勢講をおこなうようになったとの言い伝えがあります。
味噌を濁流に、大根を流木に見立てて食べることで水害を封じます。
講の当番はその年に大根を多く作り、約50~60本準備します。大根を煮たり講に参加するのは男性のみです。講が終わると女性や子どもにも大根がふるまわれます。 |
|---|
| 認証番号 | 13 |
|---|
| 認証日 | 平成30年3月22日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 下打波白山神社・中神神社の祭礼 |
|---|
| 団体等名 | 下打波区 |
|---|
| 特色 | 白山神社は、泰澄が白山開山の折に山内家に宿泊した時にほおの木で作ったイザナミノミコトが御神体であり、県指定文化財のカツラの木が境内にあります。
中神神社は、江戸時代に平べえという人が洪水後の川に流れてきた仏像をお祀りしたことが始まりの集落の神社で、字、名字が中神となったいわれでもあります。
下打波区の全戸は、昭和48年ごろまでに住居を大野市街地等に移しましたが、住民が集まる機会を持つために、毎年8月17日に両神社に集まって祭礼を行い、絆を深めてきました。 |
|---|
| 認証番号 | 14 |
|---|
| 認証日 | 平成30年3月22日 |
|---|
| 分野 | 伝統芸能 |
|---|
| 名称 | 稲郷里神楽 |
|---|
| 団体等名 | 稲郷青年会 |
|---|
| 特色 | 始まりは不明ですが、天狗の面には「延宝9年 」(1681年)と墨書されていることから、その頃にはすでに舞われていたものと考えられます。村人の安全と五穀豊穣を願い、9月第2日曜日に八幡神社に奉納される里神楽です。
天狗面には「奉上 八幡大菩薩 願主 土蔵市右ヱ門」の墨書があり、奉納に先立ち、笛、太鼓の囃子方は、この 土蔵家に集合してから神社まで吹流しを行います。
神楽最後の乱獅子は頭の役が大きく反り返る動きをする勇壮な舞となっています。
境内に土俵が作られ、神楽の終了後に子ども相撲が行われます。 |
|---|
| 認証番号 | 15 |
|---|
| 認証日 | 平成31年3月14日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 陽明町一丁目1区の不動明王祭 |
|---|
| 団体等名 | 陽明町一丁目1区 |
|---|
| 特色 | 昭和2年に町内で見つかった不動明王像(石像)を有志で祀ってきました。昭和14年にお御堂を建てて安置し、不動明王祭りを始めました。8月第1土曜日夕方から大宝寺による法要を行っています。
平成21年に町内の寄進により御堂の建て替えと雨雪を避けるための建屋を造り、区で管理しています。
また、日々のお花、お茶のお供えを2名の区民が継続しています。 |
|---|
| 認証番号 | 16 |
|---|
| 認証日 | 平成31年3月14日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 明倫町1区による乳地蔵のご祈祷 |
|---|
| 団体等名 | 明倫町1区 |
|---|
| 特色 | 羽根田家の裏庭にあった地蔵を「もっと大通りに出て、世の中の人のために働きたい」という夢のお告げにより、本願清水(糸魚町)近くに祀られるようになったと、言い伝えられます。
この地蔵に、米をお供えして、その米を一週間、 本願清水に浸してお参りをします。その米でおかゆを炊いて食べると、乳の出がよくなるという伝承があります。
明倫町1区では、4月の篠座神社祭礼前の土・日に、地蔵堂の清掃と、明倫町の曹源寺による祈祷をしています。
日々の管理には近所の方に協力していただいています。 |
|---|
| 認証番号 | 17 |
|---|
| 認証日 | 令和2年3月23日 |
|---|
| 分野 | 生業 |
|---|
| 名称 | 穴馬紙 |
|---|
| 団体等名 | 穴馬紙大すきの会 |
|---|
| 特色 | 穴馬紙は、江戸の初めより旧穴馬村にて漉かれ、当時は年貢として納められていました。水に強く丈夫で虫が付きにくいのが特長で、障子紙や帳簿等に使われていました。冬の副業として盛んに紙漉きが行われていました。
戦後間もなく廃れましたが、旧和泉村教育委員会に在籍していた社会教育指導員が中心となって復活させ、和泉小学校児童の卒業証書作りを通して穴馬紙を伝えてきました。
数年前に和泉公民館職員が作業を引き継ぎ、地元の有志が加わり、平成29年に「穴馬紙大すきの会」を発足。現在、30代から70代の16名の会員で活動を行っています。
和泉に自生している楮と糊空木を原料とし、加工に薬品は一切使わず、全ての工程を手作業で行うなど、昔と同じ方法で漉いています。 |
|---|
| 認証番号 | 18 |
|---|
| 認証日 | 令和2年3月23日 |
|---|
| 分野 | 伝統芸能 |
|---|
| 名称 | 奥越太鼓 |
|---|
| 団体等名 | 奥越太鼓保存会 |
|---|
| 特色 | 荘園時代より大野の地で行われてきた太鼓は、やがて「豊年太鼓」や「雨乞い太鼓」として発展し、人々に親しまれ伝承されてきました。
第二次世界大戦によって衰退しましたが、昭和36年、大野商工会議所と奥越観光連盟が中核となり、今日の『奥越太鼓保存会』の前身である『奥越曲太鼓朋友会』が結成され、幼児から成人まで多くの市民に伝統芸能を伝承し、奥越太鼓の保存・育成に努めています。 |
|---|
| 認証番号 | 19 |
|---|
| 認証日 | 令和3年2月28日 |
|---|
| 分野 | 生業 |
|---|
| 名称 | アジメ漁 |
|---|
| 団体等名 | 奥越漁業協同組合「アジメ漁」保存研究会 |
|---|
| 特色 | アジメとはアジメドジョウの略で、中部・近畿地方の河川中・上流域に分布する日本固有の純淡水魚である。
アジメ漁はその捕獲の特徴から「アジメ落とし」、「滝分け」ともいわれ、その発祥は定かではないが、大正時代には行われていたと推測され、その伝統漁法は和泉地区で現在も引き継がれている。6月下旬に入札により仕掛け場所を決定し、9月末まで捕獲が行われている。
料理方法は、かつては越冬のための蛋白源として「なれずし」が主であったが、近年は唐揚げが主とした料理になっている。捕獲量が少ないため、市販されることはほとんどなく、一般の人もなかなか食べられない。 |
|---|
| 認証番号 | 20 |
|---|
| 認証日 | 令和4年2月24日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | お箸始め |
|---|
| 団体等名 | 川合区 |
|---|
| 特色 | 川合道場に伝わる正月行事である。
毎年1月1日に集落内の全戸から人々が道場に集まり、御酒と雑煮をいただくもので、集落での食べ始めである。
行事の始まりは不明だが、大正の初めには行われていた。 |
|---|
| 認証番号 | 21 |
|---|
| 認証日 | 令和4年2月24日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 深井の講 |
|---|
| 団体等名 | 深井区 |
|---|
| 特色 | 「観音講」「庚申講」「二十三夜講」を、集落の春日神社観音堂やふれあい会館で行っている。
観音講は、市の文化財(彫刻)に指定されている「木造子安観音」に対する講である。1月・2月を除いた毎月行う。
庚申講は、2カ月に一度、偶数月に行う。床の間に「青面金剛」の掛軸と供え物を飾る。
二十三夜講は、1月のみ行う、月待ち行事の一つ。
いずれも行事の始まりは不明。 |
|---|
| 認証番号 | 22 |
|---|
| 認証日 | 令和4年12月9日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 新四国八十八ヶ所お砂踏み法要 |
|---|
| 団体等名 | 大宝寺 |
|---|
| 特色 | 大宝寺境内に四国八十八ヶ所霊場の石仏が安置され、各霊場から持ち寄ったお砂が埋納されている。毎年9月1日に法要が営まれ、大宝寺住職の先導の元、参拝者はお砂の上を踏みわたる。この法要は、大正10年の石仏安置以来、続けられている。
平時は厨子内に納めている旧丹生寺本尊である山王権現像を祭壇に祀っており、また、かつては大般若経の転読が行われていることから、檀家にとどまらず地域住民など広く参拝を促す勧進を目的とした行事だったと推測できる。 |
|---|
| 認証番号 | 23 |
|---|
| 認証日 | 令和4年12月9日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 水神さんの参詣 |
|---|
| 団体等名 | 小矢戸区 |
|---|
| 特色 | 小矢戸地区は背後の山に奥行きがなく、水源として不十分なため生活水に困ることから古くから湧水地を大切にし、水神である罔象女神を祀っている。始まりは不明だが、昭和初期にはすでに行われていた。
この祭礼は、毎年6月の第一日曜日に執り行われ、準備を含めすべて地区の婦人会が主催する。祠の紅白幕は婦人会役員が縫って作り、毎年掛け替えており、清浄を保っている。
地区の行事は他にもあるが、この参詣は欠かしたことはない。 |
|---|
| 認証番号 | 24 |
|---|
| 認証日 | 令和6年1月31日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 鉛筆供養 |
|---|
| 団体等名 | 中荒井町1丁目区 |
|---|
| 特色 | 地区の左義長に合わせ、使い古した鉛筆を供養することで子どもの学力向上などを祈願する行事。
子どもの代表者が行事の中心的役割を担っており、子どもらは自身が地区の一員であることを強く認識できる。 |
|---|
| 認証番号 | 25 |
|---|
| 認証日 | 令和6年1月31日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 阿難祖八坂神社の祭礼 |
|---|
| 団体等名 | 阿難祖領家区・阿難祖地頭方区 |
|---|
| 特色 | 阿難祖領家区・阿難祖地頭方区の境に建つ八坂神社の祭礼を、両区が1年交代で担当している。
鎌倉時代以前には両区は合わせて「阿難祖村」だったが、「下地中分」によって分割されたと考えられることから、分割以前の両区の関係を留めていると思われる。 |
|---|
| 認証番号 | 26 |
|---|
| 認証日 | 令和7年2月18日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 上据区の田休み |
|---|
| 団体等名 | 上据区 |
|---|
| 特色 | 集落内の浄土真宗寺院の脇陣に十一面観音を安置し、住民が主動して管理する。
一般に一向専修を宗旨とする浄土真宗寺院において密教系の仏尊が安置され、住民によって維持管理がされているところに、教義より住民の信仰心への寄り添いが窺われる。 |
|---|
| 認証番号 | 27 |
|---|
| 認証日 | 令和7年2月18日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 太田白山神社の注連縄づくり |
|---|
| 団体等名 | 太田区 |
|---|
| 特色 | 白山神社の秋祭りに際し、住民が共同して注連縄を綯う。
かつては住民が稲わらを1束ずつ持ち寄った。これは各家の穀霊を集合させて、集落全体の豊作を祈願していたと思われる。
現在は稲わらの持ち寄りはないが、作業を共同するところに、かつての痕跡を認めることができる。 |
|---|
| 認証番号 | 28 |
|---|
| 認証日 | 令和7年2月18日 |
|---|
| 分野 | 年中行事 |
|---|
| 名称 | 元町1区2班の火伏のご祈祷 |
|---|
| 団体等名 | 元町1区2班 |
|---|
| 特色 | 住民が持ち回りで「宿」をつとめて火伏の祈祷を行い、各家の代表が集まる。
城下町西端に位置する当地区は、町人地の出火が武家地および城内に延焼することがないよう、江戸時代を通じて防火対策が徹底されてきた。宿役として全住民が当事者意識を持つところに、防火意識の維持が認められる。 |
|---|