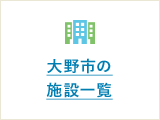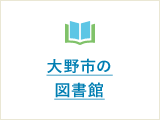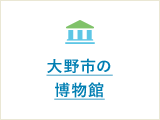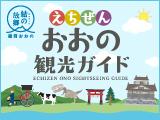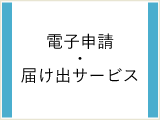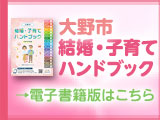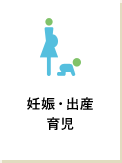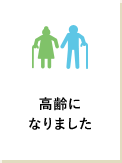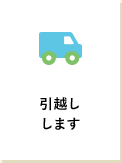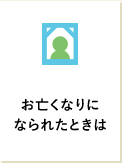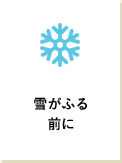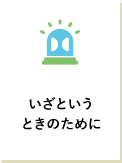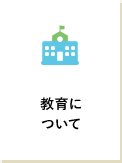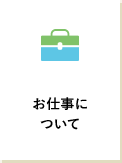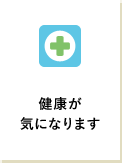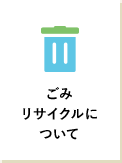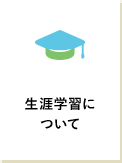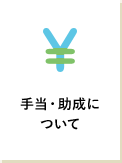介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業
大野市では、高齢者の皆さんの介護予防と日常生活の自立を支援するため、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を実施しています。総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」から構成されます。
介護予防・生活支援サービス事業
対象
- 要支援1・2の認定を受けた人
- 基本チェックリスト(健康長寿課の窓口で実施する25項目の質問票)により生活機能の低下が見られた人
事業内容
訪問型サービス
- 訪問介護相当サービス(従来のホームヘルプサービス。ヘルパーによる身体介護や生活援助)
- 訪問型サービスA(市の研修を修了した家事援助員等による生活援助や見守り的援助)
- 訪問型サービスC(市の保健師等による3~6ヶ月の短期集中サービス)
通所型サービス
- 通所介護相当サービス(従来のデイサービス。食事・入浴の提供や日常生活動作訓練)
- 通所型サービスA(3時間程度のミニデイサービス。体操やレクリエーション、創作活動、趣味活動)
- 通所型サービスC(リハビリ専門職による3~6カ月の短期集中トレーニング)
介護予防ケアマネジメント
心身状態や日常生活の状況に応じ、自立した生活を送ることができるよう、どのようなサービスを、どのくらい利用するかをご本人やご家族と相談しながら、ケアマネジャーが支援計画(ケアプラン)を作成します。
一般介護予防事業
対象
65歳以上の全ての人と、その活動を支援する人
事業内容
ふれあいサロン
閉じこもりがちな高齢者が気軽に集まれる場所です。交流を通じて介護予防や生きがいづくりに取り組みます。地区の集会場などで月1~2回開かれています。
利用方法
総合事業を利用したいとき、日常生活で困ったことがあったときは、健康長寿課内の地域包括支援センター(結とぴあ2番窓口)にご相談ください。
心身状態や日常生活の状況を確認し、ご本人に合った支援を受けたり、地域の介護予防教室等に参加することができます。
【問い合わせ】
健康長寿課 地域包括支援G(大野市地域包括支援センター) 電話:65-5046
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ