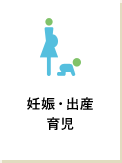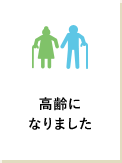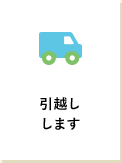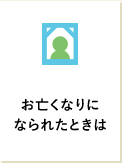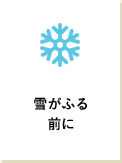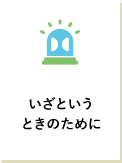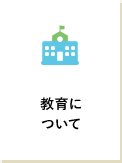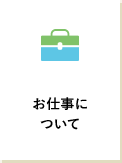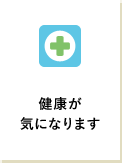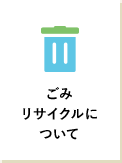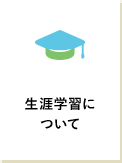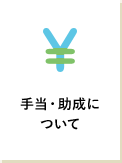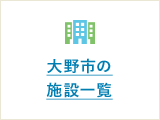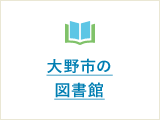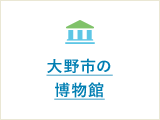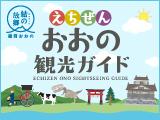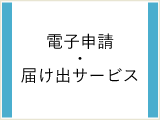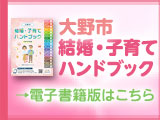大永4年(1524年)から慶長13年8月12日(1608年9月20日)
飛騨守、兵部大輔
天正3年(1575年)、越前大野郡に所領を与えられる。後に剃髪して兵部卿法印と称し、豊臣秀吉に従い、飛騨高山3万8千石を領治。その後の幾多の軍功により、天正13年(1585年)、秀吉から飛騨一国を与えられた。慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いでは東軍に与し、美濃国郡上八幡城攻などの功を賞されて二万石を加増、初代高山藩主となる。
生年不明、文禄3年(1594年2月)没
従五位下、侍従
天正12年(1584年)、越前東郷城主(大野城入城年不明、金森氏移封後大野を治めたものか)。天正17年(1589年)、近江肥田城主、文禄3年(1594年)、朝鮮出兵で病没。
天文10年(1541年)から慶長5年10月6日(1600年11月11日)
従五位上、侍従、紀伊守
豊臣氏の一族といわれる。豊臣秀吉に早くから仕え、天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いに参加する。天正15年(1587年)の九州征伐にも参加し、その功績により播磨立石城主となった。のちに越前大野8万石、文禄3年(1594年)に越前府中10万石と栄進を重ね、最終的には越前北之庄21万石を領した。慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いでは西軍に与し、降伏直後に病死。
天正11年(1583年)から慶長15年8月8日(1610年9月24日)
従三位、参議
文禄元年(1592年)、豊臣秀吉から越前国大野郡において5万石を与えられる。慶長5年(1600年)の関ヶ原の合戦に際し、秀雄は父信雄の意向に従い西軍に属するが、敗戦。改易された。
生年不明、慶長12年(1607)没
北ノ庄藩(福井藩)藩主結城秀康の家臣。城代として大野城に在城。慶長6年(1601年)に入城か? 慶長12年(1607年)、秀康に殉死。
父正明の没後、大野城主を継ぐが、父の殉死が幕府の禁に触れて改易。慶長14年(1609年)追放か?
慶長14年(1609年)、入城。
慶長6年8月5日(1601年9月1日)から(寛文6年2月3日(1666年3月8日))
従五位下、出羽守、従四位下、侍従兼任、従四位上、左近衛権少将。
結城秀康の三男。元和2年(1616年)、上総姉ヶ崎1万石を与えられる。寛永元年(1624年)、大野5万石。寛永10年(1633年)、信濃松本7万石。寛永15年(1638年)、出雲松江18万6,000石。
(直政と直基の間2年間、丸岡藩主本多成重預かり?)
慶長9年3月25日(1604年4月24日)から慶安元年8月15日(1648年10月1日)
従四位下、侍従、大和守
結城秀康の四男。寛永元年(1624年)、勝山3万石。寛永12年(1635年)、大野5万石。正保元年(1644年)、出羽山形15万石。慶安元年(1648年)、姫路15万石に国替えを命じられるが、赴く途上で死去。
慶長9年11月24日(1605年1月13日)から延宝6年6月26日(1678年8月13日)
従四位下、侍従、土佐守、但馬守
結城秀康の六男。寛永元年(1624年)、木本2万5千石。寛永12年(1635年)、勝山3万5千石。正保元年(1644年)、大野5万石。
明暦2年1月5日(1656年1月31日) から 享保6年4月21日(1721年5月16日))
従四位下、若狭守。(藩主引退後は市正)
松平直良の三男。延宝6年(1678年)、父直良の跡を継ぐ。天和2年(1682年)、明石6万石。
寛永8年(1631年)から天和3年閏5月25日(1683年7月19日)
正保3年(1646年)、従五位下能登守。延宝7年(1679年)、従四位下。延宝8年(1680年)、侍従。
大老 土井利勝の四男。延宝7年(1679年)から天和元年(1681年)まで老中職。天和2年(1682年)、大野4万石。
▲土井 利知(利治改め)
延宝2年4月18日(1674年5月23日)から延享2年2月8日(1745年3月10日)
従五位下、甲斐守
天和3年(1683年)、10歳で家督を継ぐ。元禄8年(1695年)、幕命により丸岡城受け取り。享保7年(1722年)から寛保元年(1741年)まで奏者番。寛保3年(1743年)、隠居。
享保3年9月24日(1718年10月17日)から延享3年8月16日(1746年9月30日)
従五位下、伊賀守
寛保3年(1743年)、家督を継ぐ。「江戸法令」・「大野家中法令条々」、伝馬規定など、藩の法制整備を行なうが、在位3年で死去。
寛保元年10月7日(1741年11月14日)から文化4年11月5日(1807年12月3日)
従五位下、能登守
延享3年(1746年)、6歳で家督を継ぐ。洪水、凶作、大火が相次ぎ、藩の財政が困窮する。天明3年(1783年)に勝手向御用掛を創設するなど、財政改革を行うが失敗。文化2年(1807年)、隠居。
安永6年6月27日(1777年7月31日)から文政元年6月4日(1818年7月6日)
従五位下、右京亮、中務少輔、甲斐守、造酒正
近江彦根藩主・井伊直幸の十男。寛政3年(1791年)5月、土井利貞の四女・松と婚約し、利貞の婿養子となる。文化2年(1805年)11月8日、家督を継ぐ。文化7年(1810年)3月10日、隠居。文武両道の名君とされる。
天明3年6月4日(1783年7月3日)から文政元年5月17日(1818年6月20日)
従五位下、甲斐守
下総関宿藩主・久世広誉の十一男。文化6年(1809年)8月、越前大野藩主・土井利義の養子となる。文化7年(1810年)3月10日、利義の隠居により家督を継ぐ。財政難に見舞われる。文政元年(1818年)5月17日、死去。
文化8年4月3日(1811年5月24日)から明治元年12月3日(1869年1月15日)
従五位下、能登守(没後従三位)
土井利義の長男。文政元年(1818年)、8歳で家督を継ぐ。天保13年(1842年)4月27日、利忠は自筆をもって「更始の令」を発布。藩政改革を行い、効果を挙げる。文久2年(1862年)、隠居。明治15年(1882年)、旧藩士たちにより、大野城ふもとに「柳廼社」が建立され、祭神となる。
嘉永元年7月19日(1848年8月17日)から明治26年(1893年)3月29日
従五位上、能登守(明治に至って正四位。子爵)
文久2年(1862年)、家督を継ぐ。元治元年(1864年)、天狗党が大野藩領を通過。明治元年(1868年)4月12日、新政府より箱館裁判所副総督に任命される。
 ※ここをクリックすると、大野市博物館のトップページに戻ります。
※ここをクリックすると、大野市博物館のトップページに戻ります。