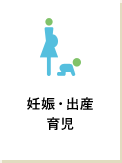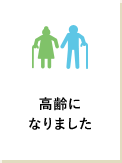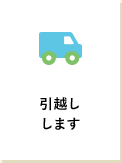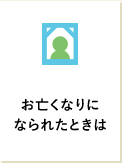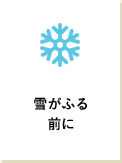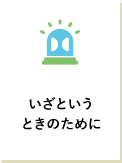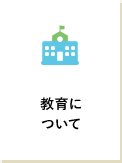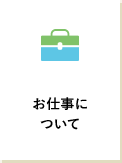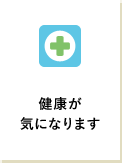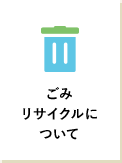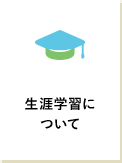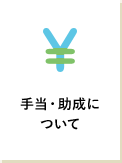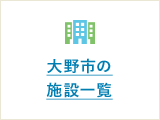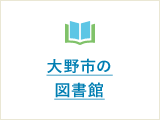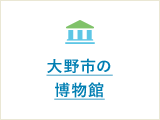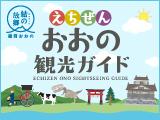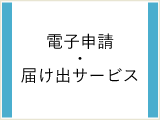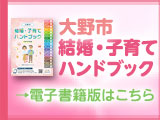イトヨ学習室 天然記念物の本願清水やイトヨについて学習しよう!
イトヨの生態概要と本願清水 における調査 森 誠一(1998年11月)
1 イトヨの概要
1) イトヨの仲間たちと分布
イトヨはトゲウオ科イトヨ属Gasterosteusの一種である。世界には大きく分けて五種類のトゲウオがおり、北アメリカやヨーロッパ、ロシアの広い範囲の沿岸域や平地を中心に生息している。この仲間は水産的にほとんど無価値なので、わが国ではその存在すらあまり知られていないが、実はサケ科魚類と並んで北半球に
日本には大きく分けて、二種類のトゲウオがいる。イトヨ属とトミヨ属である。イトヨ属の仲間は、現在、形態からイトヨ(G.aculeatus form trachurus)とハリヨ(G.a.f.leiurus)とに二分されている。しかし、生活史の上では、遡河型(イトヨ)と淡水陸封型(イトヨとハリヨ)があり、形態および生活史から三群が認められる。従来、淡水型イトヨおよびハリヨの祖先型は、遡河型イトヨに類似し分化したものであると考えられている。 トミヨ属にはトミヨ、イバラトミヨ、
2) わが国のイトヨ
イトヨ類は、わが国においては北緯35度以北に分散的かつ局所的に分布し、現在は激減傾向にある。このイトヨには淡水型と遡河型の二つのタイプがある。前者は一生淡水域で過ごし、後者は繁殖のため川を上り、産卵後は死ぬというサケのような生活史をもつ。イトヨ類の淡水型は本州では湧水地を中心に、夏期でも水温20度以下の水域を中心に生息している。この淡水型の分布地は、十水系前後であるにすぎない。しかも、本州産淡水型は減少の一途を辿っている。福井県大野盆地、栃木県那須地方、福島県会津盆地が知られているが、いずれも絶滅に瀕しているのが現状である。それらはそれぞれ
この淡水型の局所的分布に対し、遡河型イトヨは山陰地方(日本海側)および関東地方(太平洋側)以北の沿岸平野部に、3~6月を中心に繁殖のために大量に遡ってくる。しかし、これもまたすでに、「動物学雑誌」の1900年代初頭に年々減っているとの記載がある。今や、太平洋側は宮城県が南限となっており、仙台市を流れる河川で発見されると、新聞ネタになるくらいになっている。現在、関東地方で採集されることはほとんどない。非常にまれに、茨城県での報告がある程度である。
元来、北方系の魚であるイトヨ類は日本の分布地が南限になり、特に大野市のイトヨ生息地はイトヨ属の南限地に位置する。したがって、彼らの生存のためには、夏でも水温20度以上にならない湧水域(年中15度前後)が、生息する上で不可欠である。湧き水はイトヨにとっで生命の源”というに等しい。逆に、冷水には強く、水面に氷が張っていても平気で餌を食している。
3) イトヨの形態
本種は形態的な特徴があり、背に垂直に立つ三本のトゲをもち、腹部には真横に突き出す一対のトゲをもっている。さらに、尻鰭の前に小さなトゲが一本付いている。これらのトゲは根元が蝶番のようになっていて、普段は畳んでいる。ライバル雄に対して攻撃したり、雌を誘ったりするときに、トゲを立てる。
このトゲは、
こうした適応論的な説明の他に、トゲのなかでも特に背トゲは
また、形態的特徴として、イトヨを含めてトゲウオの仲間にはコイ科などのような平たく円形に近い鱗がない。“
最近、淡水型か遡河型か、あるいは完全
日本における遡河型イトヨと淡水型イトヨとが別種であるという見解が定着しつつある。ただし、淡水型イトヨは、現在知られている個体群を一括して議論することは避けるべきだろう。なぜなら、淡水型と呼ばれているイトヨは淡水型になった年代の変異が大きく、例えば場所によって数十万年から数千年という開きがあると考えられ、また陸封化されてわずか数十年という年月の個体群もあるからだ。この変異は考慮しなければならない。そのためにも、きわめて単純で基礎的な資料、つまり生息地の分布調査が必要である。
4) イトヨの繁殖行動
イトヨは繁殖期になると、雄は口先からえら蓋および腹面にかけてが赤く、かつ体側部が鮮やかな青色になる。この
一方、雌は産卵するだけで、営巣にも育児にも一向に関与しない。雌は卵を産みっ放しで、後は再び卵をもつためにもっぱら餌を食べるのみである。1年と数カ月しか生きられない多くのイトヨにとって、卵をはらみ産卵する雌は多大のエネルギーを必要とする。そこで、ナワバりの形成、家づくり、子育てのすべては、雄の役割ということになっている。このイトヨの行動研究はティンバーゲン(ノーベル賞授賞者)によって進展し、生物学の一分野である行動学の基礎になった。
5) トゲウオ学の周辺
イトヨに限らず、日本にはトゲウオ類を題材とする研究者は少ない。海外ではその分布の広さとティンバーゲン以来の歴史もあって、研究者は多く、したがって毎年多くの論文が発表されている。おそらく、もっとも論文数の多い
1990年代に入って、トゲウオを扱った研究は、今まで以上にホットな状態にある。特に、系統進化学的な目的から形態、生態、行動、遺伝など多岐にわたるアプローチがなされるようになった。それはポイントさえ掴めば飼育が比較的容易で、成長が早く、多くは一年で成熟し世代交代が早いことや、脊椎動物としてサイズが小さく扱い易いなど、トゲウオ自体の性質によるところが大きい。
こうした中、1984年と1994年に第1回、2回のトゲウオ国際シンポジウムがオランダで開かれた。その最初のシンポジウムはティンバーゲンのトゲウオ研究開始50周年をも記念して開催された。これらの集大成として、1994年にBe11&Fosterが編集したThe Evolutionary Biology of the Threespine Stickleback(Oxford大学出版、イギリス)と、1995年にはバッカーとセイフンスター編集によるSticklebacks as Models for Animal Behaviour and Evolution(E.J.Bri11出版社、オランダ;Mori,1995)の2冊が刊行された。いずれも、充実したデータ量に基づいた多岐にわたるアプローチに対して高く評価されている。さらに、来年度(1999年)、カナダで第3回のトゲウオ国際シンポジウムが開催される。
2 本願清水 の調査結果(固体群組成を中心に)
1) 目的と方法:繁殖状況の調査
営巣場所の位置確認や営巣地と周辺の物理環境(水深、流速、水草の被度、岸からの距離、最短巣までの距離など)などを測定などし、イトヨの繁殖にとって何が重要であるかを解析することを目的とした。しかしながら、実際に調査を行なえた6月中旬は
したがって、繁殖の結果としての個体群の状況(個体数、体長、性比、その時点の熟度など)を把握するために、春産卵期に生まれた個体が4cm前後の未成魚になる11月中旬にイトヨを採集調査した。
2)体長組成
11月17日に、中央部を網で仕切り2区画(上流側と下流側)に分けて、イトヨを総計1898尾を採集し、体長を計測した。上流側で計394尾(うち未成魚324尾)、下流側で1504尾(うち未成魚1208尾)を採集した。
体長50mmは成魚として性別を判定し、熟度を計測した。性別は頭部の相対的な大きさ(雄の
上流側と下流側の区域ごとに、イトヨの体長分布を示す。いずれの区域も体長40~50mmの個体が多く、体長45mm前後に大きなピークがあった。これらの個体は、他の個体群の研究結果(Mori,1985; Mori, 1987; Mori &Nagoshi,1987)からであるが、今年の春生まれと推定される。このことは大野市のイトヨを調査した田中ら(1973)の結果がらも推定できる。ただし、60mmを超えるような個体は、咋年
特筆すべき事項として、体長85mmを超える雌の大型個体が採集確認された。体長85mmというサイズは、遡河型イトヨの平均体長よりも大きいほどである。これは成長率が高いからというものでなく、寿命が長くなった結果であろう。それは餌条件や営巣条件などがよくなく、繁殖を次のシーズンまで持ち越した場合であるかもしれない。すなわち、
また、体長30mm前後に小さなピークが認められた。これらは今年の夏に生まれた個体と思われる。すなわち、遡河型イトヨの繁殖期が春に限られているのに対して、この淡水型イトヨは長期化していることを現わしている。この春にとどまらない長期の繁殖期は、湧水性の淡水型イトヨに認められる特性である。
本調査結果の体長組成は、以前の調査結果や他地域の個体群と比較して考慮する必要と価値がある。
3)繁殖状況
・熟度
上流側では雄47尾、雌23尾であり、雄が雌よりもほぼ2倍多かった。一方、下流側では、性比がほぼ1(150尾:146尾)であった。産卵に参加できる抱卵雌(段階5)は、上・下流側とも認められなかった。また、営巣している可能性のある雄は上流側で2尾、下流側で1尾であった。
雄は熟度2の個体がもっとも多く、熟度3の個体は上流側で3尾、下流側に1尾が認められた。雌は普通の熟度3が多く、次いで少し痩せている熟度2の個体の順であった。
・営巣活動
6月の調査では、上流側の岸沿いに3個の巣が認められた。うち2個の巣には雄が定位して、なわばり行動をしていた。しかしながら、いずれにも巣内の卵は確認できなかった。イトヨの巣は選択的に20~30cmの水深に作られることが多いが、本願清水では50cm前後であった。これは
11月は上流側の奥の岸沿いに、卵の入っていない巣が1個だけ確認された陸下流側には巣の形跡すら認められなかった。
4)他の魚類
イトヨ以外に上流側ではドジョウ2尾、アブラハヤ2尾、下流側でアブラハヤ21尾が採集された。これらの魚類はイトヨを摂食することはないが、卵を食することがあるかもしれない。ただ、卵食い行動をするのは、同種のイトヨに依ることが多いと考えられる。この生息地はイトヨがきわめて
5)本願清水 のイトヨ
しかしながら、
大野盆地のイトヨ生息地は1970年代からでも、かなりの減少をしている。現在では、
3 大野市の本願清水(ほんがんしょうず)におけるイトヨの保全のために
イトヨの存続のためには、下記の2点が最重要
1)湧水の確保(夏の高水温時に、20℃以下であること)
2)水域を拡張および危険分散として、生息地の複数化(中野地区など)
ここでまず重要なのは、生息地の面積をとにかく大きくすることである。極論すれば、下流域に水温が少々高くなる時期(常時でなく)があっても構わない。
湧水量は変動(おもに冬期に減退)があるため、分布域も変化するだろう。冬期には、分布域を広げる可能性がある。しかし、下流にいったイトヨが夏期に、
いずれにしても最終的なところでは、
イトヨの存在意義と事業価値を、地域住民に理解啓蒙するために世界を念頭に置きつつ、市の内外に情報発信する方策を考慮する。その母体として、例えば「イトヨ保全委員会」の常設設置をし、池やセンターの管理運営をする。
また、事業完成後、早い内に『トゲウオ全国サミット』(第2回)を開催し、その環境保全への理解を深めていくよう計画する。(森 誠一 1998年11月)