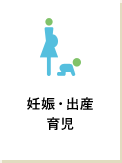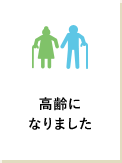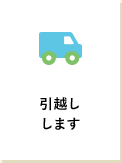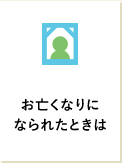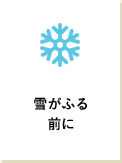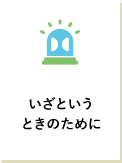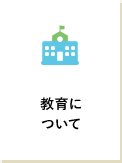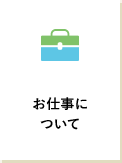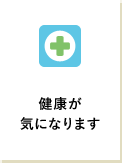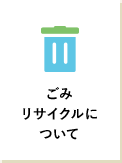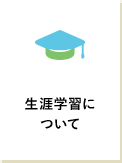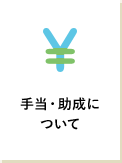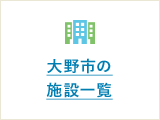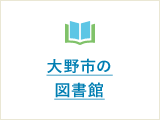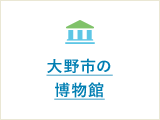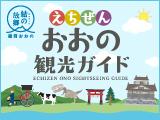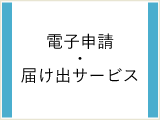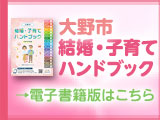令和7年9月定例会 提案理由説明
令和7年9月第446回大野市議会定例会の開会に当たり、最近の諸情勢や市政の重要課題の取組状況について申し述べますとともに、提案いたしました各議案の概要について御説明申し上げます。
大野市戦没者追悼式を、御遺族をはじめ議員各位、区長連合会や経済・教育・福祉関係の代表者、小中学校の児童生徒代表など約130人のご参列のもと、先月21日に挙行し、戦争の犠牲者に思いをはせ、哀悼の誠を捧げました。
終戦の日から80年という大きな節目の年を迎え、戦争の記憶を風化させることのないよう、世代を越えて語り継いでいきます。
伊藤竜也さんが、今月27日からインドで開催される「ニューデリー2025世界パラ陸上競技選手権大会」の男子100メートルに日本代表として出場されます。
伊藤さんのご活躍を期待しています。
それでは、本市の重要課題の進捗状況について、第六次大野市総合計画基本構想の六つの分野の基本目標に沿って御説明申し上げます。
最初に、「こども分野 未来を拓く大野っ子が健やかに育つまち」について申し上げます。
本年3月に策定した「大野市こども・若者計画」を推進しています。
教育委員会は、夏季休業中の子どもの居場所づくりとして、「学びと遊びと体験の広場」を乾側、小山、上庄、富田、阪谷の放課後こども教室の児童を対象にエキサイト広場総合体育施設を主会場に実施しました。
参加した40人の児童たちは、化石クリーニングやヨガの体験、星空の講座などで、充実した夏休みを過ごしていました。
大野市青少年健全育成推進大会を、7月27日に学びの里めいりんで開催しました。
これからの大野を語る少年の主張や10年後の自分の夢を語るパネルディスカッションがあり、登壇した子どもたちが堂々と発言する姿がありました。
若者の交流拡大や活動促進に向け、7月に市内の事業所などから若者20名が集まり、活動チーム「結リンク 大野で永年界隈」が立ち上がりました。
今後は、若者が集いたくなる活動内容や場所を具体化するため、若者自身でアイデアを出し合います。
令和8年4月の小学校再編に向けて、準備が進められています。
新有終南小学校再編準備委員会及び新富田小学校再編準備委員会の3回目の合同会議が7月3日に開催され、統合校同士の事前交流の状況や学用品購入の支援内容、スクールバスの運行準備などの確認が行われました。
学校改修について、下庄小学校と開成中学校、陽明中学校では、駐車場の舗装や自転車小屋の整備などの外構工事を進めており、11月末の完成を見込んでいます。有終南小学校と富田小学校では、改修工事を順次進めており、今後は、壁や床、天井など建物の改修とともにスクールバス発着場などの工事を進めていきます。
小学校で使用しているタブレット端末を本年度末に入れ替えるため、県と共同して調達に取り組んでいます。タブレット端末購入に係る契約に関する議案を、本定例会に提出しています。
県中学校夏季総合競技大会が7月2日から21日まで県内各地で開催され、相撲競技で福井相撲クラブに所属する陽明中学校3年の室谷優輝さんが無差別級で優勝し、熊本県で開催された全国中学校体育大会の団体の部と個人の部に出場しました。
次に、「健幸福祉分野 健幸で自分らしく暮らせるまち」について申し上げます。
本年は猛暑が続き、福井県に熱中症警戒アラートが先月25日までに21回発令され、このうち、大野市の暑さ指数が33を超えた日が1日ありました。
暑さ指数33を超えると予想される場合は、SNSや防災メール、消防署による巡回広報等により市民への周知を行います。平時も「涼み処」として市民が利用できるクーリングシェルターは、本年度新たに日本郵便株式会社と、株式会社ファミリーマートと協定を締結し、公共施設で12カ所、民間施設で18カ所となりました。
百寿、米寿を迎えられる方に対し、健康と長寿を祝い、長年にわたり郷土の発展に貢献されてきたことに感謝の気持ちを伝えるため、今月、記念の品を贈ります。先月25日時点で百寿を迎えられる方は21名、米寿を迎えられる方は260名いらっしゃいます。
令和6年度に給付した「定額減税補足給付金」に不足が生じる方等に対して給付する「定額減税不足額給付金給付事業」について、先月下旬、対象と見込まれる方へ案内通知を発送しました。対象者への迅速な給付に努めます。
第60回福井県スポーツ少年大会が、県下のスポーツ少年団員約950名の参加のもと、大野市・勝山市を会場に昨日開催されました。スポーツ活動を通して、団員相互の交流と友情を深めました。
令和8年1月23日から25日にかけて、九頭竜スキー場とDAINOUスポーツランドを会場に、中部7県から役員・選手団を迎え、常陸宮賜杯第76回中部日本スキー大会が開催されます。先月19日に実行委員会を設立し、開催に向けて準備を進めています。
次に、「地域経済分野 歴史・風土と新たな強みを生かした活力あるまち」について申し上げます。
国道158号が仮設道路の完成により、7月下旬から岐阜県方面との往来が可能となったことから、新聞やテレビ、ウェブを活用し、県内をはじめ北陸エリアや中京エリアに観光情報を発信し、誘客を図りました。
その効果もあり、7月下旬の道の駅の来場者数は、「九頭竜」が6,600人、「越前おおの 荒島の郷」が36,321人で、対前年比それぞれ約40%増となりました。
紅葉シーズンに向けての誘客促進については、プレミアム付きデジタル地域商品券を発行し、市民や観光客の消費喚起につなげ、事業者を支援していきます。
また、民間事業者による多様かつ魅力的な宿泊施設の整備を支援する経費を計上した補正予算案を、本定例会に提出しています。
本年度の「結のビジネスプランコンテスト」に、30件のアイデアの応募があり、一次審査を通過した5件が、10月開催予定の最終審査会に向け、専門家によるブラッシュアップ支援を受けています。
「大野の逸品創出事業」に、本年度新たに8社が参加しており、これまでにグループ勉強会を開催し、中小企業診断士による伴走支援を受けています。
昨年度に支援した事業者の一部商品については、品評会などへの出品を目指し、引き続き伴走支援をしています。
「越前おおの地域応援商品券」は、昨日、商品券の販売と使用期限が終了しました。
先月28日時点の購入額は、約2億3,000万円、購入率は全体の約96.9パーセント、使用された額は約2億300万円となり、市内の消費行動につながっています。
働き方改革の促進や仕事と子育てが両立できる職場環境づくりの取組につきましては、大野市働く人にやさしい企業に1社を、大野市子育て世代にやさしい企業に2社を認定しました。
市ホームページで、それぞれ認定した企業の取組を紹介しています。
中部縦貫自動車道大野油坂道路の工事の進捗につきましては、和泉・油坂区間のトンネル6本のうち5本が貫通し、残る1本が掘削に向け準備が進められています。
橋梁は、20橋すべての上部工事に着手し、4橋が上部工まで完成しています。追加対策が必要な新子馬巣谷橋につきましては、地すべりを抑止する対策に着手していると伺っています。
要望活動につきましては、7月9日の大野市議会中部縦貫自動車道等交通対策特別委員会と中部縦貫自動車道大野油坂道路整備促進連絡協議会の合同要望のほか、先月5日に中部縦貫自動車道建設促進福井県協議会、7日には大野・勝山地区広域行政事務組合の活動に出席しました。
今後も必要な予算の確保と一日も早い県内全線開通に向け、安全な工事の進捗を願うとともに、関係の皆様と国への要望活動に取り組みます。
県と市が進める六呂師高原活性化構想の一環として、奥越前パークコンソーシアム合同会社により整備が進められていた、キャンプ場「ソラトダイチ」が7月19日にオープンし、日本一美しい星空を楽しめる六呂師高原に新たな魅力が生まれました。
また、昨日と一昨日には当該キャンプ場運営者らで組織する実行委員会による「六呂師スターリーミュージックフェスティバル2025」が開催され、県内外から多くの来場があり、日本一美しい星空の下で音楽を楽しんでいました。
本市の夏の一大イベントで58回目を迎えた「おおの城まつり」が、先月13日から16日まで開催されました。
13日の「大花火大会」では、夜空に打ちあがった約2,500発の大輪の花に大きな歓声が沸きあがりました。
15日、16日の越前おおのおどりと合わせて延べ72,000人の市民や観光客がまつりを楽しみました。
本年は、猛暑かつ降雨量が少ないことから、全国的に水涸れによる農作物への被害が広がっています。
本市においては、今冬の積雪量が多かったこともあり、水涸れによる被害の報告はありませんが、梅雨時期に雨が少なかったこと、高温が続いたことから、水稲の品質低下が危惧されています。
収穫時期を迎え、台風や天候不順による水稲への影響がないことを願っています。
生産者の農業経営意欲の維持向上を図るため、10か所の土地改良施設の整備、棚田地域の保全を目的に行う共同作業に必要な資機材の購入について、県事業に採択されました。
これらへの支援に必要な経費を計上した補正予算案を、本定例会に提出しています。
市内畜産農家の乳牛が、一般社団法人日本ホルスタイン登録協会が主催する「第16回全日本ホルスタイン共進会北海道大会」に、福井県代表として出品されます。
出品に要する経費の一部補助に必要な経費を計上した補正予算案を、本定例会に提出しています。
ツキノワグマの先月25日時点の出没件数は、39件と昨年同時期を下回っておりますが、7月には市街地での目撃情報が3件ありました。
猟友会や県、警察などの関係機関・団体と警戒にあたり、幸いにしてクマによる人身被害は起きませんでした。
ツキノワグマ出没対策連絡会を7月15日に開催し、関係機関が情報を共有し、今後、出没が多い時期を迎えることから、市民の安全確保を第一に、被害の未然防止に努めることを確認しました。
第9回「山の日」全国大会FUKUI2025は、「未来へつむぐ、ふくいの山々 ―感謝と共生のこころを次世代へ― 」をテーマに、記念式典が先月11日に結とぴあで、歓迎フェスティバルが10日、11日に本市と勝山市で開催されました。式典のトークイベントや歓迎フェスティバルのワークショップを通じて、参加者は山の魅力や豊かな自然の恩恵を感じていました。
次に、「くらし環境分野 豊かな自然の中で快適に暮らせるまち」について申し上げます。
第三期大野市環境基本計画及び大野市水循環基本計画について、年度内の中間見直しに向け、4月から5月にかけ市民や事業者を対象とした環境・水に関するアンケート調査を実施しました。また、7月には、大野市環境保全対策審議会及び水循環推進協議会において両計画に掲げる施策の進捗状況に対する中間評価を行いました。
8月1日の「水の日」に九頭竜川ダム統合管理事務所と連携し、麻那姫湖青少年旅行村で小学生親子を対象とした水に親しむイベントを開催しました。友好交流市である岩倉市の親子も参加し、多くの方が交流しました。
9月10日の「下水道の日」を中心に、下水道に対する理解、関心を高めるため、全国の地方自治体や関係団体が下水道の普及啓発を行っています。
本市においては、小学生親子を対象とした下水処理センター見学とプチアウトドア体験を先月23日に開催しました。また、生活排水が公共用水域に与える影響が汚水処理方法によって異なることを市報9月号に分かりやすく掲載するとともに、本日から12日まで市民ホールでパネル展示を行っています。
また、「見えない地下水を守る下水道~大野市の水循環都市への挑戦~」をテーマに、香川大学教授からの話題提供や、大野市水循環アドバイザーによる講演を、今月14日に結とぴあで開催します。
次に、「地域づくり分野 みんなでつながり地域が生き生きと輝くまち」について申し上げます。
市民協働による住民自治検討委員会の4回目の会議が、先月26日に開催されました。
これまでの会議で地域づくりや住民自治などについて意見交換した内容を踏まえ、検討委員会として「市民協働によるこれからの住民自治方針(案)」が取りまとめられました。
(仮称)乾側地域交流センター整備につきましては、7月から敷地の造成などを行っており、今月から交流センター本体の基礎工事に着手する予定です。
令和9年度中の全体整備完了を目指し、工事を進めていきます。
大野市総合防災訓練を、来月26日に下庄小学校を主会場に実施します。
大雨と大規模地震の発生により、電気・水道・道路寸断等ライフラインに甚大な被害を受けたと想定し、住民避難訓練をはじめ、水難救助訓練、水道復旧訓練や道路啓開訓練などを実施します。
第74回福井県消防操法大会の小型ポンプ操法の部で、大野市消防団を代表して出場した、乾側地区を管轄する第3分団が優勝しました。
選手をはじめ関係者の皆様に敬意を表するとともに、地域防災の中核を担う消防団の活躍が、地域防災力の向上につながることを期待します。
第46回大野市美術展を先月27日から5日間、結とぴあで開催し、市内外の美術愛好家の洋画や彫刻工芸、書道などの作品269点が出品されました。入賞作品のうち市民の作品は、本日から9日まで市民ホールで展示を行います。
COCONOアートプレイスにおいて、企画展「シルクスクリーンなう」を開催中であり、多彩な色合いやレトロな風合いで描かれた版画を、今月15日まで展示しています。
来月4日からは、小コレクター運動により本市にゆかりのある作家、靉嘔の新作版画11点を中心に靉嘔企画展を開催します。
第59回大野市総合文化祭は、「次世代につなごう 大野の文化」をテーマに、来月19日の吹奏楽の発表を皮切りに、市民による書道や生け花などの作品展示と民謡や舞踊などの舞台発表を、結とぴあや文化会館を中心に11月3日まで開催します。
荒島岳東方の約1億2900万年前の前期白亜紀の地層から発見された化石が、国内最古級となる新たなトカゲ類であることがわかりました。4年前から進めてきた福井県立恐竜博物館との共同調査による研究の成果で、日本の恐竜時代の陸生脊椎動物の多様性を知る重要な資料です。
先月5日からくずりゅう化石ラボ ガ・オーノで展示しています。
次に、「行政経営分野 結のまちを持続的に支える自治体経営」について申し上げます。
全国的な表彰では、地縁による団体の代表者として、長年にわたる住民自治組織の発展向上への顕著な功績が認められ、安川昭夫さんと林 幹雄さんが、全国自治会連合会表彰を受賞されました。
受賞された両氏の、今後ますますの御活躍を期待申し上げます。
姉妹都市である茨城県古河市と本市との友好の絆を強固にし、交流人口の拡大に寄与するため、古河市合併20周年を記念し、11月8日から9日にかけて、本市から市民及び関係機関の代表者などが古河市を訪問する姉妹都市交流ツアーを実施します。
現在、広報おおのと市ホームページで参加者を募集しています。
公共施設の最適化を目指し、これまで、公共施設の再編を進めてきました。
施設の解体に、地方交付税措置のある有利な起債が令和8年度まで活用できることから、これを活用し財政負担の軽減を図りたいと考えています。
このため、旧和泉体育館や旧宝慶寺いこいの森などの解体実施設計に必要な経費を計上した補正予算案を、本定例会に提出しています。
健康保養施設あっ宝んどのプール施設と九頭竜温泉平成の湯について、利用実態に即した開業時間などにするため、各施設の設置条例の一部を改正する条例案を本定例会に提出しています。
大野市地球温暖化対策実行計画に基づき、市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量を削減するため、市有施設の照明機器のLED化を計画的に進めています。
本年度導入する4施設に係るリース契約に関する議案を、本定例会に提出しています。
自治体情報システムの標準化について、令和7年度末までに国が示す標準仕様に適合したシステムへ移行する準備を進めてきました。
11月以降に本稼働するために必要な経費を計上した補正予算案を、本定例会に提出しています。
第六次大野市総合計画の前期基本計画に掲げる成果指標の目標達成に努めるとともに、令和12年度までの5年間を計画期間とする後期基本計画の策定作業を進めています。
大野市総合計画審議会が7月28日に、また、第六次大野市総合計画後期基本計画策定幹事会が先月4日に開催され、後期基本計画の素案について協議されました。
それでは、ただ今上程されました各議案の概要について、御説明申し上げます。
予算議案につきましては、一般会計、特別会計、企業会計の7会計で補正予算案を提出し、御審議をお願いするものです。
一般会計の主なものといたしましては、宿泊施設の改修や農業用用排水施設の整備への支援に必要な経費、自治体情報システムの標準化に伴う運用経費、施設の解体に向けた実施設計に係る経費など、合計1億91万1千円を追加し、予算累計額を206億3,307万9千円とするものです。
各特別会計、企業会計の主なものといたしましては、自治体情報システムの標準化に伴う運用経費などを計上しています。
次に条例議案といたしましては、「大野市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例案」「大野市健康保養施設設置条例の一部を改正する条例案」など7議案を、その他議案といたしましては、「公共施設LED照明導入業務の契約締結について」「大野市小学校タブレット端末購入業務の契約締結について」「和解について」の3議案を提出しています。
また、一般会計及び特別会計、企業会計の決算認定に係る4議案を提出していますので、合計21議案について御審議並びに御審査いただきますようお願いします。
各議案の内容については、それぞれ担当部局長が説明しますので、慎重に御審議の上、妥当なる御決議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。