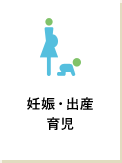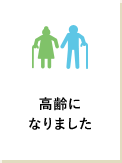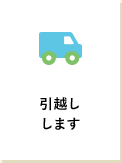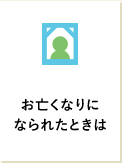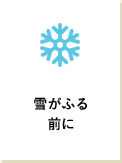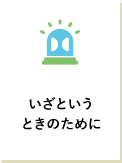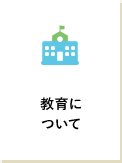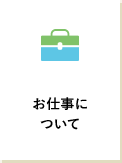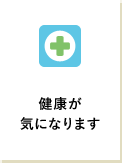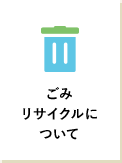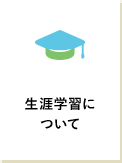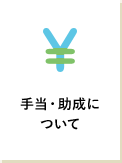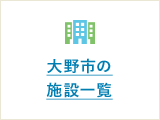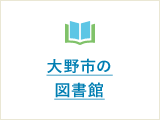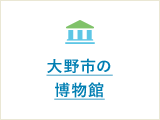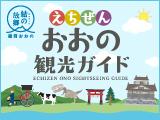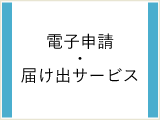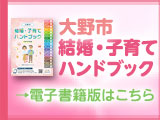受け取ることのできる年金
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として10年の受給資格期間を満たした人が65歳になったときから受けられる年金です。
詳しくはこちらをご覧ください。![]() 老齢基礎年金(外部サイト)
老齢基礎年金(外部サイト)
65歳前でも受けられるの?
老齢基礎年金は希望により、65歳前に繰上げて受けることもできます。しかし、一定の割合で年金額が減額され、65歳以降も一生減額された年金を受け取ることになります。また、希望により66歳以降から受け取ることもでき、その場合一定の率で増額されます。
詳しくはこちらをご覧ください。![]() 繰り上げ請求(65歳前からの受給)(外部サイト)
繰り上げ請求(65歳前からの受給)(外部サイト)![]() 繰り下げ請求(66歳以降の受給)(外部サイト)
繰り下げ請求(66歳以降の受給)(外部サイト)
障害基礎年金
病気やケガで障害の状態にある場合に、初診日(初めて病院にかかった日)が国民年金被保険者期間中、20歳前もしくは60歳以上65歳未満の未加入期間にある人が対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。![]() 障害基礎年金(外部サイト)
障害基礎年金(外部サイト)
遺族基礎年金
国民年金加入中に死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(10年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1,2級の障害のある子は20歳まで)支給されます。
18歳未満の子がいない場合は支給されません。
詳しくはこちらをご覧ください。![]() 遺族基礎年金(外部サイト)
遺族基礎年金(外部サイト)
付加年金
定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、1月あたり200円の付加年金が老齢基礎年金に加算されます。
- 保険料の免除を受けている人、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付できません。
詳しくはこちらをご覧ください。![]() 付加年金(外部サイト)
付加年金(外部サイト)
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納付した月数と半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数が、36月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したとき、その方と生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
- 付加保険料を3年以上納付している場合は8,500円が加算されます。
詳しくはこちらをご覧ください。![]() 死亡一時金(外部サイト)
死亡一時金(外部サイト)
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。
年金額は夫の受けることのできた老齢基礎年金の4分の3です。
詳しくはこちらをご覧ください。![]() 寡婦年金(外部サイト)
寡婦年金(外部サイト)