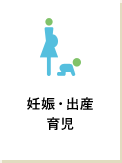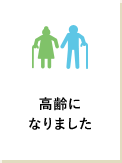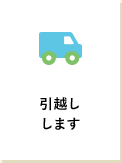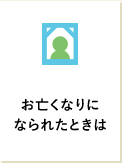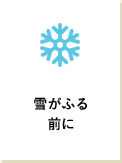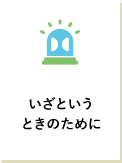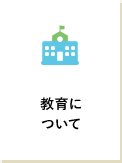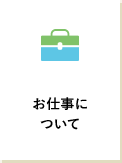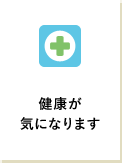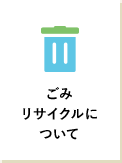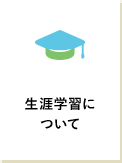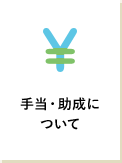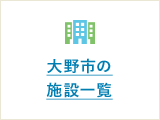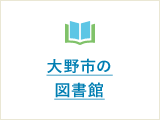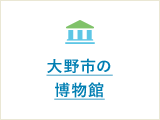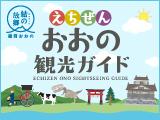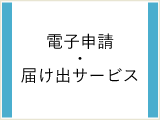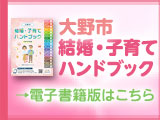【特集】道の駅産直の会 大野の味を自分たちの手で
※本ページの掲載内容は、広報おおの令和7年8月号に掲載された情報を、ウェブ用に再編集したものです

道の駅産直の会とは
道の駅「越前おおの 荒島の郷」と「九頭竜」の直売所を、もっと魅力的なものにしたい。そんな思いから平成31年2月に、道の駅の運営者と市が連携して立ち上げたのが「大野市道の駅産直の会」です。
全国で初めて、道の駅へ自由に出荷できる仕組みを導入し、地元の新鮮な野菜や山菜、加工品などを年間を通して届けています。令和7年6月末現在で193人が会員として登録しています。
今回の特集では、産直の会で活躍する生産者の皆さんの思いや、会の活動内容を紹介します。
主な活動
地元産品の出荷・販売
新鮮な農産物や加工品を道の駅で販売し、道の駅の来場者に大野の味を届けています。
季節のイベント開催
季節に合わせたイベントを開催しています。お客さんとの交流が増え、リピーターづくりにもつながっています。
イベント例(令和6年度実績)
- 春の収穫祭(山菜などの直売)
- スイートコーン収穫体験
- 秋の収穫祭(サトイモと米の直売)
- サトイモ株割り体験
研修会
品質や技術の向上を目指した各種研修会を企画し、実施しています。
研修会例(令和6年度実績)
- 夏野菜栽培研修会
- 鳥獣害対策研修会
- 雪の下野菜栽培研修会
- 新規作物(春キャベツ、春タマネギ)の試験栽培
- エコ農業研修会
- リサイクル肥料研修会
Voiceー会員の声ー
谷口 忠臣さん、健 さん、美忠 さん(千歳)

道の駅で予想以上の反響
産直の会には発足当初から加入しています。当初はあまり売れ行きの期待はしていませんでしたが、予想以上に商品が売れ、驚いています。特にサトイモは、1日に300パックほど売れることがありました。
今では、サトイモは生産量の約5割、米は約3割が道の駅への出荷分となっています。
付加価値を生む土作り
栽培では特に土作りにこだわっています。化学肥料には極力頼らず、土本来の力を引き出すようにしています。おいしさだけでなく、付加価値を感じる農産品を作りたいと思っています。
手間が掛かる分、価格は少し高くなりますが、その価値を理解してくれるお客さんがいて、リピーターも増えてきているので、自信を持って出荷しています。
大野の魅力広げたい
これからも米やサトイモの品質を高め、道の駅を通じて大野の農産品の魅力を広めていきたいです。
また、多くの人に会へ加入していただき、一緒に地元の特産品を盛り上げていければと思います。
清水風月堂 代表 清水 俊邦さん(高砂町)

地域を元気にしたい
道の駅のにぎわいづくりの手助けができればと、荒島の郷のオープン当初から産直の会に加入しました。自分の仕事が地域の活性化につながればと思っています。
ハナモモの酵母で新商品
主に「サトイモとマイタケのピザ」や「でっち羊羹パン」など、地元の食材を生かした商品を出荷しています。
7月からは、大野のハナモモから採った天然酵母の食パンを、道の駅限定で販売しています。天然酵母は発酵の調整が難しいですが、他にはない大野の味を届けたいという思いで試作を重ね、ようやく完成にたどり着きました。
挑戦する楽しさ
産直の会の研修では、道の駅の来場者データを分析する機会がありました。良いものであれば高価格でも売れることが分かり、新たな商品開発に役立っています。
これから道路状況が改善されれば、お客さんはさらに増えるはずです。大野には魅力的な商品を作っているお店がたくさんあります。ぜひ一歩踏み出し、一緒に大野の味を市外や県外の人に届けてみませんか。
和楽農園 代表 米村 正悟 さん(塚原)

会社員からブドウ農家へ転身
以前は福祉の仕事をしていましたが、別の形で地域に貢献できないかと考え、3年前から農業の道に進みました。大野では果樹栽培に取り組む人が少ないため、挑戦してみたいと思い、県の研修施設で2年間学んだ後、昨年から大野でブドウ畑の整備を始めました。
大野ならではの味を目指す
今年は樹木の生育を優先し、来年からの収穫を目指しています。
ブドウは寒暖差のある土地に適しているといわれ、大野ならではの味わいが出せるのではと期待しています。将来的には観光農園や、福祉と農業を結びつける取り組みにも挑戦し、地域の活性化に貢献したいと思っています。
道の駅で広がる可能性
以前、試験的に作ったスイカを道の駅で販売した際には、他の品種との違いを伝えながら試食をしてもらい、お客さんが喜ぶ様子を間近で見られ、とても良い経験になりました。自分の思いを直接伝え、それを受け取ってもらえる楽しさや手応えを感じました。
産直の会では、栽培や販売方法についての研修が充実しているので、これからも他の会員と情報交換や交流を続け、自分の視野や可能性を広げていきたいです。
羽生 啓一さん(下据)

農業を学び、受け継ぐ
農家に生まれ育ち、幼い頃から自然と農業と触れ合う環境に育ってきました。親が元気な間に、実家の農業について知ろうと思い、今年から農業に関することを学び始めました。
大野の水と伝えたい味
大野の名水で育つ米や野菜には、この土地ならではのおいしさが詰まっています。その味を多くの人に伝えていきたいです。
道の駅には少量からでも出荷できるので、米やサトイモのほか、これまで自家消費に留めていたナツメやグミなどの珍しい作物を、消費者に届けることができるようになりました。
作る喜び、届けるうれしさ
農業は決して楽ではありませんが、手塩にかけて育てた作物をお客さんに選んでもらえることは、お金以上の喜びを感じます。道の駅への出荷を始めてから「もっと良い作物を作りたい」という思いが強まりました。
今は8月中の出荷を目指してマクワウリを育てています。すっきりとした素朴な甘さが特徴で、お客さんに喜んでもらえるよう、出荷の日まで丹精込めて育てていきます。
産直の会に関するQ&A
Q.どんな商品を出品できますか?
A.米や野菜、山菜、果物、加工品(弁当や惣菜、漬物など)のほか、木工や手芸など工芸品も出品できます。
Q.会費や出荷料はかかりますか?
A.入会金6000円、年会費1000円(市外は3000円)、販売手数料は15パーセントからです。
Q.どの程度の量から出荷できますか?
A.1点からでも出荷できます。
Q.毎日出荷しないといけませんか?
A.自分のペースで出荷できます。毎日でなくても大丈夫です。
Q.初めてでも大丈夫ですか?
A.事前の研修制度があるので、安心してください。
Q.出荷の条件はありますか?
A.農産物は栽培日誌をつけている、加工品は営業許可を受けた施設で製造するなどの条件があります。詳しくは問い合わせてください。
出荷の流れ

(1)栽培・製造
道の駅に並べる農産物や加工品を生産する
(2)出荷準備
商品をチェックし、生産者ラベルを貼る。必要に応じて説明書きも添える
(3)出荷作業
価格を設定し、商品を売り場に陳列する
(4)追加出荷
道の駅からの売上数のメール連絡をもとに、不足する場合は商品を追加する
(5)商品引取り
1日の終わりに、売れ残った商品を毎日引き取る(日持ちのするものは引き取り不要)
(6)代金受取り
月末締めで、翌10日に出荷者の指定口座へ、代金が振り込まれる
データで見る道の駅

来場者数
77万3979人 (令和6年度2駅合計)
直売所販売額
2億6205万円 (令和6年度2駅合計)
売れ筋商品ランキング
※ランキングは令和6年度の販売数量(点数)順です
農林産品部門
1位 サトイモ
2位 シイタケ
3位 マイタケ
4位 キュウリ
5位 山菜類
加工品部門
1位 舞茸弁当
2位 丁稚ようかん
3位 生ドラ
4位 パン
5位 ブッセ
道の駅へ出品しませんか

道の駅産直の会では、商品を出品する会員を募集しています。全国から訪れるお客さんに、自慢の一品を届けてみませんか。興味のある人はぜひ申し込んでください。
入会方法
申込書をいずれかの道の駅へ提出する
※申込書は道の駅とホームページで配付
※審査を経て結果の連絡があり、手続きが完了すると出荷を始められます
申込み・問合せ先
- 道の駅九頭竜 (☎0779-78-2300)
- 道の駅「越前おおの 荒島の郷」(☎0779-64-4500)